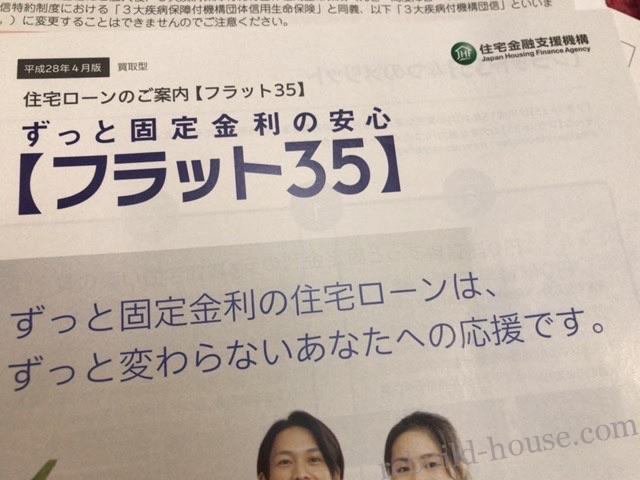二世帯住宅を建てるにあたって、
親世帯が注文住宅を建てる資金を全額負担してくれる太っ腹な親は
現実的にはそう多くはないはずです。
親世帯と子世帯が建設費用を割合を決めて出し合う場合が多いと思うのですが
今回はそんなお金の話、二世帯住宅を建てる場合の住宅ローンの組み方の実例を挙げて書いてみました。
二世帯住宅の資金のやりくりの仕方は色々ある

二世帯住宅を建てる決め手になったのは一緒に住む親の援助があるから!
という人の中にはいるのではないかと思います。
何千万円ものお金をローンが組めるとはいえ、簡単に決断はできないものですよね。
親世帯との半同居、同居というハードルもありますが、建築費用の面でも色々と考えることはあります。
今回は3例を挙げて書いてみました。
土地は親の名義で上物(建物)は子供名義で建てる場合
親の土地の上に子供が建物代を負担して建設する場合は
親の名義の土地に家を建てるという書類を一筆交わすことが必要になります。
親とはいえ、一応他人の土地の上に登記人と違う人が家を建てることになりますからね。
基本的にはハウスメーカーにその旨の相談をすると、
司法書士さんにお願いしてくれて一通りの手続きをしてサインさえすればOKという形になると思います。
ただし、司法書士さんと入れたり、書類の手続きなどで諸費用が数万円かかる、というのは知っておいてくださいね!
土地の一部も建物の一部も両方親子で建てて住宅ローンを組む場合
この場合は親が働いている場合は親子それぞれが塩梅を決めて
住宅ローンの審査を普通に行ってローンを組んでそれぞれが支払いをするという場合に行うケースです。
メリットは、お互いの住むエリアはそれぞれがきちんと支払いをするということで、棲み分けができるというところ。
デメリットは団信にも2名義分入ったり、住宅ローンの審査が2人分かかったりと少々コストがかかるところ。
親にも歳老いてからのローンを組むことになるので負担や借りられる金額が少なくなったりするので
大きな二世帯住宅を建てる場合には注意が必要です。
いくら金利が低くても、負債を親子共々抱えることになるので将来のことを考えると不安・・・と思う人は多いでしょう。
親がまだ若い世代の二世帯住宅なら、選択肢として入りそうな例ですね。
親の土地に子供が家を建てて親子リレーローンを組む場合

我が家の場合は、
親がまだ現役で働いているけれど、親の負担は限りなく少なくしたい
だけれど子供の収入だけだとちょっと住宅ローンの審査が通るか心配だったので
セゾンが出している、親子リレーローンという商品を利用して住宅ローンを組みました。
他のローン会社でも同じように親子リレーローンを扱っている会社はあります。
我が家は、このセゾンの住宅ローンが一番融資金額が多かった
というのが決めた理由です。
融資金額が多いということは、それだけ見栄を張って負債を抱えて家を建てることになるので
いいイメージはあまり持たれないと思いますが
一応夫婦共働きなので
二世帯合わせて3人仕事をしていれば払えるという金額には設定しました。
支払いは親子の名前が両方記載されたもので来ます。
我が家の場合は、二世帯住宅を建てるにあたって必要になった
建て替え前の家屋の解体費用やその他住宅ローンに組み込めずに現金で必要になったものを親世帯に支払ってもらったので、
その代わり、住宅ローンの支払いは子世帯が行なう
と決めて現在も絶賛住宅ローン支払い中です。
二世帯住宅で親と同居
というので関係性や住み心地を考えるのも大事ですが
「建てるときにどちらがいくら出すのか、そもそも親に資産はどれくらいあるのか」
聞きにくいことですが、
家に関する話は
ハウスメーカーの営業さんを間に入れたりと工夫をしてでも一度はきちんと話をしてから
いい家を建てていきたいですね!
二世帯住宅の資金負担割合と住宅ローン選びのポイント

二世帯住宅を建てるにあたって、親世帯と子世帯の資金負担割合や、住宅ローンの組み方は重要な決定事項です。
負担の分担やローンの選択肢がスムーズに決まれば、建設費用や返済に関する不安を軽減できます。
ここでは、二世帯住宅を建てる際に検討すべき資金負担とローンの選び方についてのポイントを紹介します。
親子で資金負担を分けるメリットとデメリット
二世帯住宅の建設資金を親世帯と子世帯で分担する場合、各世帯の負担割合や支払いの役割分担が重要です。
分担の仕方により、それぞれの資金計画や返済が異なり、生活にも影響を与えるため、
メリットとデメリットを理解しておきましょう。
親世帯と子世帯の負担割合を決めるメリット
親世帯と子世帯がそれぞれ負担することで、一人当たりの負担が軽減され、
無理のない範囲での資金計画が可能となります。
また、建設費用の分担により、親世帯と子世帯の意見が反映されるため、各々の要望が取り入れやすくなることもメリットです。
負担割合に伴うデメリットとリスク
一方で、親世帯の収入状況や、子世帯の将来的な生活設計に応じて返済計画が変動することがあるため、
将来の金銭負担を見据えた慎重な計画が必要です。
また、いずれかが収入減少や転職などで返済が難しくなった場合、負担が偏る可能性もあります。
親世帯と子世帯が負担割合を調整する方法
お互いの支払能力に合わせ、例えば「親世帯が建設費用の一部を負担し、子世帯がローン返済を担当する」
といった柔軟な方法もあります。
資金や将来の生活変化に応じたバランスの取れた方法を検討し、計画を立てると良いでしょう。
二世帯住宅の住宅ローンの組み方と資金管理の工夫
親世帯と子世帯が協力して住宅ローンを組む場合、複数の選択肢があります。
親子リレーローンや各世帯の個別ローンなど、家庭の状況に適したローンを選ぶことで、
返済負担やリスクを減らすことが可能です。
親子リレーローンのメリットと利用条件
親子リレーローンは、親世帯が現役で働いている場合に組むことができ、
子世帯に返済義務が引き継がれる形で、長期的に返済できる仕組みです。
親世帯の収入を考慮した融資額が増えるため、広めの二世帯住宅を希望する場合には最適です。
親子でローンを分担するデュアルローンの活用方法
デュアルローンは、親世帯と子世帯がそれぞれローンを組み、負担を分担する方法です。
これにより、各世帯が独立して支払いを行えるため、支払いの透明性が確保されます。
ただし、各世帯のローン審査が必要となり、名義や契約内容が異なる場合も多いため、事前に確認しておきましょう。
親世帯名義でローンを組む際の注意点
親世帯の名義でローンを組む場合、親が引退後の年齢を迎えると返済に影響が出る可能性があるため、
年齢や健康状況も考慮する必要があります。特に高齢の親世帯が負担する場合は、
団信(団体信用生命保険)や保険の内容も確認しておくことが大切です。
二世帯住宅の生活費分担とトラブルを防ぐ工夫
二世帯住宅では、建設費用だけでなく、日々の生活費やメンテナンス費用の分担も重要です。
負担割合が不明確だと、将来のトラブルの元になりやすいため、
生活費の分担方法やトラブル防止のためのルールをしっかり定めておくことが大切です。
共用スペースの管理費用をどう分担するか
二世帯住宅では玄関やリビングなどの共用スペースを維持管理するための費用が発生します。
これらの費用は親世帯・子世帯のどちらが負担するのか、または分担するのかをあらかじめ決めておきましょう。
水道光熱費の分担と支払い方法の工夫
共用部分の水道光熱費は、両世帯の消費量を合計して分担するケースが多いです。
たとえば、世帯の人数や使用量に応じて、どちらが多めに支払うかを決める方法もあります。
また、共用スペースにメーターを設けることで、実際の使用量に基づいた支払いが可能です。
共有設備の修繕費を公平に分担する方法
共有設備が故障した場合にかかる修繕費も、あらかじめ分担方法を定めておくと、トラブルを未然に防げます
年間の修繕費を分担して積み立てておき、大きな支出が発生した際に対応できるようにすると便利です。
二世帯住宅の生活費でトラブルを防ぐためのルール
生活費の分担で不平等感が生じないように、ルールを事前に設けることも大切です。
具体的な分担内容や支払方法を定めることで、円滑な二世帯生活が可能となります。
親世帯・子世帯で生活費を分担する際のポイント
生活費の分担については、各世帯の収入状況に応じて柔軟に調整することが重要です。
たとえば、「共用スペースの費用は親世帯が多めに負担し、日常の光熱費は子世帯が担当する」
といった分担方法が有効です。
家族間での金銭トラブルを避けるための口座管理方法
生活費の支払いに使う共用口座を作成し、
両世帯が定期的に一定額を口座に入金することで、金銭トラブルを防ぎやすくなります。
口座の管理を透明にし、支払いの負担割合が不明確にならないよう配慮しましょう。
生活費分担のルールを文書化しておくメリット
支払いの分担ルールを文書にしておくことで、後からトラブルが発生しにくくなります。
特に長期的な生活を考えると、どのように支払いや費用負担を分担するかを明確にしておくことが、
二世帯生活の安定につながります。
二世帯住宅は単世帯の夫婦間の問題だけではないため、
住宅ローンの審査も単世帯の場合と少し異なるサービスがあったり
審査方法が違ったりと
色々と考えることが多いのですが、
ここできんと話し合い、お金のことは明確にしておかないと
生活を共にする場なので、言いたくても言い出せないモヤモヤが必ず発生します・・・
(私の場合は旦那にお金のことで言いたくても言えないことがあったり・・・w)
何事も、最初が肝心!!!
しっかり自分のプランを持って計画しましょう!